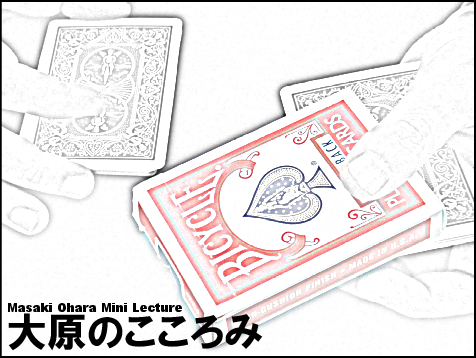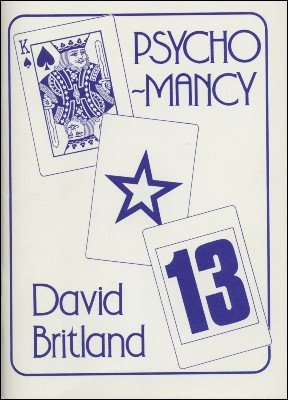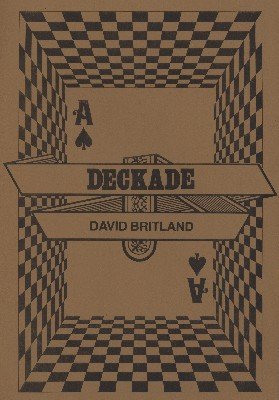Bold and Subtle Miracles of Dr.Faust
Bold and Subtle Miracles of Dr.Faust (David Hoy, 1963)
伝説のMentalist、David Hoyのあまりに大胆な手順を解説した小冊子。
David Hoyという人はメンタルマジックの世界で名声高く、伝説的な逸話がいくつもある。最近読んだところでも、Barrie Richardsonの
Act Twoで、ほとんど奇跡としか思えないBill Readingでコンベンションを静まりかえらせる場面が描写されていた。
その割に、Hoyの手順を伝える本というのは少ないようだ。ネットでざっと書誌を見た限りでは、本書の他に
Magic with a Massage、
The Meaning of Tarot、
The E.S.P. Lecture CD(LP盤の
ESP According to Hoyと同じくLP盤の
ESPecially Yoursの復刻)があるが、どれも『いわゆるマジック』からは外れる内容らしい。
Magic with a Massageはマジック集ではあるが、メインテーマは”キリストの教え”を伝える事。ゴスペル・マジックというジャンルになるのだが、日本人にはビザー・マジック以上になじみがなく、食指が動かない。
The Meaning of Tarotは単なるタロット読本(解読書?)らしい。
The E.S.P. Lecture CDも、一般に向けての”超能力”の講演。
ラインナップの謎は、Hoyの経歴を見て解けた。
元々はバプテスト教会のエヴァンジェリスト(伝道者)で、その後マジシャン、メンタリストを経て、最後は超能力者をしていたようだ。なるほどなあ。
Super-psychic:The Incredible Dr.hoyという本も出ているみたいだがこれは伝記。
そんなわけで、本書はHoyの殆ど唯一の作品集。
(他の本を知ってる人が居たら教えて欲しい)
36頁、収録作10で印刷もかなり劣悪な小冊子だが、内容は今読んで尚、あまりある衝撃を持っている。
実は寡聞にして、Hoyの高名なThe Bold Book Testの秘密を知らなかったのだ。
読んで納得、これ以上なにかを削る事も、これ以上何かを付け加える事も出来ない、このアプローチでの完成形。ヴァリエーションを目にする機会もなかろうというもの。
似たようなアプローチで、もっと手の込んだ物に、Chan CanastaのBook testがあるが、あちらが大胆さと思考能力を同時に駆使するのに比べ、Hoyの物はほとんど大胆さだけで成り立っており、演者への負担が極めて少ない。
殆ど究極のBookTestと言って過言ではないなと。
Canastaのものは、3人の観客を使う代わりに、1冊の本で、心の中で決めて貰った頁の、指定された行数目、指定された箇所の単語を読み取るというとんでもない物なのだが、いかんせん難易度が高い。
他の何作かは、いろいろなところで改案を見たせいもあって、さすがにそこまでの感銘は受けなかったが、どの手順も極めて単純化されているのが特徴であり長所と思う。
あれもこれもと詰め込まれがちなBlind Fold Actも、手の間にかざされた品物を3回あてるだけで終えるというシンプルさ。
一致するESPカードは、カードを山に重ねたりはしない。Booktestも、相手が選んだ言葉が封筒の中に収められていたりもしない。
総括、
大胆な、ずうずうしい手段、というような意味合いのBold Approachに基づいた手順は、どれも薄氷を踏むような危うさと隣り合わせだが、鮮やか。
現象もストレートなら、ハンドリングもストレートで、よどむところがない。
特に2種類のBook testと、Tossed out deckには今読んでも衝撃を受ける。極めて大胆だが、しかしかろうじて万人が演じられるぎりぎりのライン。
うん、すごい本だった。
もっとHoyの奇計を読んでみたいところであるのだが、前述の通り、本書以外にはめぼしいものがない。
確認できた限りでは、Hoy’s Bill Switchという技法と、Voodoo Dollという手順があるらしいのだが、どこに発表されたのかまでは判らなかった。