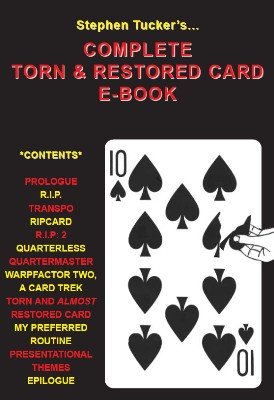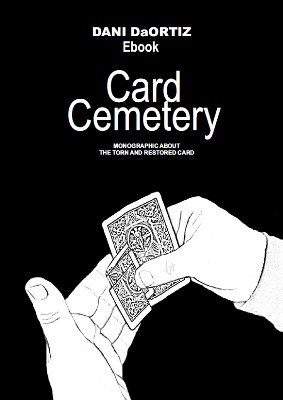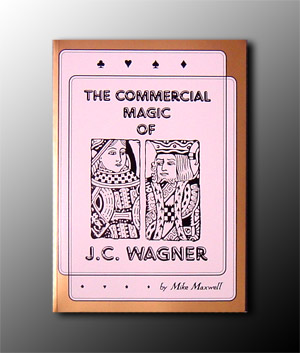The Underground Change (Jamie Badman, Colin Miller, 2002)
あーっ、疲れたぞ畜生。
数理マジックで解説が間違っていた時の再構成の労といったらもう。まあそれは後で書くとして、
技法Underground Changeと、Misdirection Monte他いくつかの手順を解説したe-book。
Underground ChangeはDVD Welcome to the Farmでも解説されているようだ。日本関西圏の某ショップでは、Misdirection Monte以外に特筆すべき事はない、とまで言いながら販売している。褒めているんだか貶しているのだか。
ともあれ。
もしこの本を知らない人が居たら、まずは紹介動画を見に行って欲しい。話はそれからだ。
昔から気になっていた本。Luceroの動画で衝撃を受け、Turnover Swith全般に惹かれた時期があったのだが、当時は英ポンドも強く見送ったのだった。
今回、またLuceroの動画を見て、やはり衝撃を受け、この本を思い出し、強い円にも後押しされて買ってみた。
最初の権利書きで、技法・手順を映像に撮ること、および技法を解説すること、が明確に禁止されているので、あまり踏み込んだことは書けないのだが、なかなか問題のある冊子。
もし見えないTurnover Switchを求めているのなら、これは違う。
Underground Switch自身は、実は過去の技法とほとんど大差ない。とある既存技法をベースに、その使用できるシチュエーションを増やした拡張版。応用範囲は広がったが、スイッチ自体のディセプティブさは変わらない。
だから他の方法より”スイッチが見えない”とか”スムーズ”とかそういう事はあんまり無いので注意されたい。例のMonteも、実のところその既存技法との併用であって、Underground Switch自体の出番はむしろ少ない。
ま、あんまり書くと、拉致されて言葉に出来ないような責め苦を受けるかも知れないのでこの辺で控えよう。(参考:http://www.youtube.com/watch?v=oQlOWHY57-I)。
その上で、やはりMisdirection Monteは凄い手順。Underground Switchの出番は少ないと言ったが、しかしこのスイッチ無くしては成立しないのも確か。このMonteなくしてUnderground Switchに価値は無く、Underground SwitchなくしてこのMonteは成立しないと言ってもいいぐらい。
一方、Monte以外の手順はどうにも今ひとつ。Badmanは様々な用途を見せてはくれるのだが、Monteのような美しいミスディレクションは無く、技術的に厳しい。読むほどにMisdirection Monteの奇跡的な完成度が浮かび上がってくる。
ま、技術的な点はおいても、カードの裏に書いた棒人間が性交を始め、あげく片方が妊娠するとかいう実にアンダーグラウンドな手順は、そうそうやれる人もいないだろうが。
むしろUnderground Switchを使わないオマケの2手順の方が面白かった。どちらもMisdirection Monteから繋がるように構築されているのだが、一つ目は、
『カードを選んでもらい、デックの中に戻す。4枚のパケットでAが一枚ずつ裏返り、全部裏向きになる。最後にまた一枚表向きになり、それがQに変わる。残りの3枚を見ると、Qに変わっている。デックをスプレットすると表向きのAが現れ、一枚のカードを間に挟んでいて、それが観客のカード』という、僕の描写力不足を加味しても、まあ意味不明な現象である。
Twisting AcesとTranspositionとSandwichをあわせたような感じ。
これが殺し屋にまつわるストーリーが加わることで、劇的にわかりやすく意味のある現象になるのが素敵だった。
もう一つはTomas Blombergの数理トリック。
DVD 21でもラストにとんでもない物を見せてくれたが、この人は数理ネタが実に上手い。数理もので、カードを数えてもらう動作も多いというのに、全体像が実にクリアーで現象が美しい。もう惚れてまいそう。この人が本出したら速攻で買うのになあ。
今回はNumerology(確かカードカレッジにも入ってたよね)みたいなトリックなのだが、別の原理を組み合わせた4 of a Kindの出現現象になっていて、すんごく不思議。セットも簡単で、レパートリーに入れたいと久しぶりに思った。
むしろMisdirection Monteより良いと思った。
ただし、冒頭で言ったようにこのトリックは解説が不足しており、かつ間違っている(たぶん)。
そこまで複雑では無いのだが、数理トリックの知識が少ないと、再構成がむずいかも。
かなり長くなったがまとめ。
Misdirection Monteだけを目当てに買えばいい。見えない汎用Turnover Switchを求めると間違い。
他の手順は今ひとつだが、可能性の羅列としては面白い。
Turnover Switchの系列全体に言えることだが、応用範囲が広そうでいて、実際に構築するとなるとなかなか難しいのだよな。まだまだ可能性が眠っている技法と思うので、クリエイティブな方にはがんばって欲しい。
あとTomas Blomberg目当てに買ってもいい。むしろこっちが本体で、Underground Switchがオマケと言っても過言では、
―――おや? こんな時間に誰だろう?
Blombergの手順、内容ミスについて。また単体で演じる場合について。
自分と、買った人のためにいちおうメモ。↓