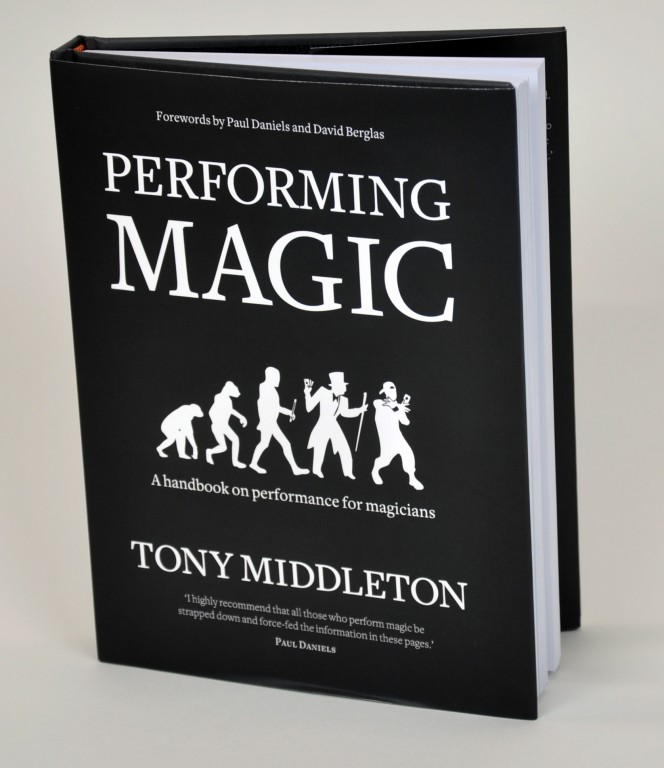Thinking the Impossible (Ramón Riobóo, 2012)
先頃発売されたスペインのマニア Ramón Riobóoの初英語作品集。
いや、これは酷い本だ。
よくもまあHermeticはこれを出したものと思う。
皆さん、本書は読まなくていい。
だって本当に酷いんだ。
酷いんだよ。
こんな手品されたら、追えるわけがなかろうよ。
『ひっかけられるのが怖いなら、Ramónには会わない方がいい』とHermeticの惹句にもあるが、ここまでとは思わなかった。生で見たら、不思議も度を過ぎて怖いレベル。
残念なことに本書への興味を失わなかった人のために、改めて。
Ramón Riobóoはスペインのマニア。
単発ではSteve BeamのSemi Automatic Card Tricksにちらほら出ていたらしいが、あの分厚くていつまでも新刊が出続けるシリーズを追ってる人は、あまりいないだろうから、無名の新人といってもいいだろう。
(一応、TamarizのMnemonicaにも作品があるが、あの分量の中からピンポイントでこの人の名前が引っかかっている人もそうそういるまい。)
さて新人というのは、決して比喩表現ではない。写真で見るとなかなかご高齢だが、前書きなどから察するに、この本の刊行時(西語版2002年)のマジック歴は10年かそこらのはず。本を出すレベルのマジシャンとしては本当に若手の部類である。
元のお仕事を50歳で退職した後にマジックを始めたらしく、その経歴が、本書を形成する一種独特なトリックの構成にも深く関わってくる。
本書の収録作品は、いわゆるセミ・オートマティックなカードマジック。
セルフワーキングとは違って、いくつかの技法や操作を必要とするものの、トリックの骨子は”原理”によって成り立っている作品群である。
Riobóoの作品は、セルフワークと聞いて思い浮かべるような煩雑さは皆無で、トリックの外観は非常に簡潔にまとめられている。まあスペリングこそ多用されるものの、そこには意味がちゃんと感じられる。ひたすらダウンアンダーをしたり、配りなおしたりという、現象の要請のために延々と操作させられるあの嫌な感じは全くない。
あまり意味のないような動作や、最初に言った約束・制限を破るような干渉もあるが、それは全体像をシンプルにする方向に働いており、客側から見ても違和感はないだろう。
基調として、観客がシャッフルした状態から行うものが多く、場合によっては殆どを観客が操作する。現象はカードあてが殆どになってしまうが、いわゆるロケーションからマインドリードまで、いろいろ。スペリング、および複数の観客(2~5)が必要なトリックが多く、その点では自分の環境には合わなかった。
プレゼンや動作の意味について詳述しているのも特徴で、デュプリケートを使ったCard to the Boxという、マニア的には”逃げ”にしか思えない解法も、ここまで構成や狙いが書いてあると、やってみたい気になる。
作品は、要求事項によって大きく5つに別れており、以下の通り。
『完全な即席:21』
『ちょっとしたセットアップ:2』
『メモライズドおよびフルスタック:5』
『デュプリケートやギミック:7』
『Treated Card:4』
Treatedっていうのは、粘着性のしかけを施したカードを指している。
ともかく、演者が”必要なこと”以外何もしていないように見えるのが、実に好み。
Finnelly Found
カードを広げていって、観客Aに1枚を覚えてもらう。
覚えたカードが含まれているだろうブロックをAに渡し、
覚えたカードを抜き出して他の人にも見せてもらう。
演者は手元に残ったカードを、別の観客Bに渡し、混ぜてもらう。
Bが適当な枚数をカットして出した上に、Aは覚えたカードを戻す。
Aは手元の残りのカードを混ぜ、適当な枚数をカットして覚えたカードの上に載せる。
A,Bの手元に残っているカードを集め、それも重ねてしまう。
これで、Aの覚えたカードが任意の枚数目にコントロールできると言ったら、君は信じるかね?
DaOrtizの数字のフォースを使ったCAANに繋げてもいいな。
Cardini Plus
5枚ずつの手を3つ配り、1つ選んで、好きなカードを覚えてもらう。
そのカードを、観客自身がデックに戻して混ぜる。
その後、演者も簡単に混ぜ、観客に渡す。
観客が自分の"心の中だけで決めたカード"のスペル分、配ると、
その枚数目から覚えたカードが出てくる。
これ、観客は、ほんとうに心の中で決めただけなんだ……。
スペリングが難しい言語なのが悔しい。
ともかくすごい本だった。
わざわざ洋書など読むくらいになると、好みも狭くなり、一冊に1~2個も当たりがあればいい方だが、本書ではすぐにレパートリーに入れたいものだけで3~4個、機会があったら演じてみたいと思う物を含めれば8~10個もあった。
できれば、みんな買わないで欲しいんだけどなあ。
なお、どれも演技はとても難しいと思う。こんな不可能状況でもってカードを当てたら、絶対どや顔してしまいそう。演じ方によってはめちゃくちゃ鼻持ちならないマジシャンになって、またぞろ『マジックを見ると腹が立つ』人口を増加させてしまいかねないので取り扱いには細心の注意を要するだろう。
しかし。Ascanio、Carroll、Tamariz、DaOrtiz、Piedrahita、そしてRamón Riobóo。スペインってのは、いったいどんな人外魔境なのか。あな怖ろしや。