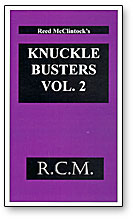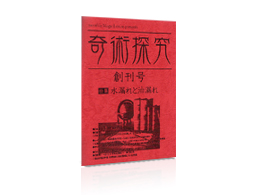2013年7月31日水曜日
"Varied Methods" Scott Robinson
Varied Methods (Scott Robinson, 2012)
Scott Robinsonのレクチャーノート。風変わりな3技法と、洗練された8手順。
Vanishing Incからダウンロード・ビデオ Pure Imaginationが出ていて、それがとても面白そうだったのでe-bookを買いました。
いえ、ビデオの目玉であるWilly Wonka Card Trickこそ入っていませんが、他の2手順、Loose Change、Differenceは収録されていますし、Willy Wonka Card Trickにしても、そのヴァリエーションであるWillie in your Pocketは解説されていてそれでお値段$5しか違わないので、それはもうこちらを買いますですよ。実体版もあるようですが、それだと$25+S&Hなのでさすがにまあそこまでは。
技法3種:Lee AsherのPulp Frictionが大変お好きだそうで、それをベースにしたカード技法2種と、コインの技法1種。このうちの1つが特につまらなくて、正直ぜんぜん役に立たなそうだなあと思っていたのですが、後の手順で実に美しい使い方をされており、良質のミステリで伏線が繋がったような快感を覚えました。やられた、と。
手順:ややマイナーなプロットが多いですが、非常に洗練されています。銅貨1枚と銀貨3枚の瞬間的な交換現象Difference、Digital DissolveのGaffless版 Loose Changeについては動画プロモにあるとおりですが、カード作品も実に素敵でした。ギミックやデュプリケートを使用することも多いですが、総じてセットに複雑さはなく、演じやすそうです。特に以下の2つが印象的。
Who's Counting:相手が言った枚数のパケットをカットするCounting on It現象。KennerなどはSybilカットして出してましたが、そういうフラリッシュ的なカットを行なわず、というかカットを行わず、デックの真ん中あたりから指定された枚数をそのままつかみ取った様に見える。
現象はマイナーで、あまり華もないですが、これは見事な構成でした。きっとたぶんとても不思議。
Willie in your Pocket:動画にあるWilly Wonka Card Trickのギミック版。角度はすこしきついですが、Bizarre Vanish的に消えたカードがポケットから現れ、そして……。こちらはギミックの使い方がとても素敵で、やはり良質のミステリを読んだような喜び。裏仕事の巧みさを褒めるのは、ちょっと本末転倒かもしれないですが、でも面白かったんだもの。あ、現象自体も大変美しいですよ。ただし、2段目が1段目の消失を食ってしまう可能性はあります。
Card、Coinの他にもCard Through the Billなどもあり、とても面白いノートでした。全体的に力が抜けていて、怪しい気配がなく、それでいて現象は鮮やか。裏の仕事も実に面白いです。また新作が出たときは入手したい所存。
なおSteve Beam編のSemi-Automatic Card TricksおよびTrapdoorの常連だそうで、本書の作品にもそこからの再録が散見されます。Semi-Automatic Card tricks、Trapdoor、興味が出てきましたがさすがにページ数が莫大なのでなかなか……。
2013年7月21日日曜日
"Knuckle Busters Vol.2" Reed McClintock
Knuckle Busters Vol.2 (Reed McClintock, 2002)
指を痛めそうな作品の詰まったコイン小冊子。
収録は3作。現象はTrio in Three、Open Coins Across~Production、そしてProductionとばらばらだが、一貫してMcClintockらしい無茶さと、鮮やかさが発揮されている。
・Three with CSB
Gary KurtzのTrio in ThreeをCSBギミックで行えるようにした物。現象もやや簡素化されており淀みないが、一部、とても気を遣うハンドリングを用いている。McClintockは、まるで「自分は出来てるから問題ない」とでも言うかのように、こういう危うい箇所をそのまま放置するのでタチが悪いが、一方でそれがこのシリーズの読み所でもあるだろう。
元となっているKurtzの手順はとかく有名であるにも関わらず、氏のまとまった作品集Unexplainable Actsには収録されていないので、まともに練習したのはこれが始めて。コインが1枚ずつカードの下に移動した後、再び手に握ったコインが全て消え、よけておいたカードの下から現れる。あまり作例を見ないが非常に面白い手順と思う。
日本語ではマジックハウス刊行のレクチャーノート ギャリー・カーツのコインマジック に解説があり、持ってもいるのだが、訳が悪いのか元の文が悪いのか、私には中間部が判読不能だった。たしかビデオには収録されているのだったかな?
・Ninth Dynasty
Open Coins Across。見えている状態で、では無いが、手を開いた状態でコインが移動していく。特に手の甲から移動する所は、本当によくやるなあMcClintock。
上手く出来たら気持ち悪そうだがこれも難しい。
そしてCoins Acrossの最後、何故かコインが9枚に増える。
なぜだ……?
・Seven the Hard Way
7枚コインのプロダクション。McClintockの代表的な作品で、Geniiにも発表されていたように思う。7枚パームから始めてしばらくOne Coinの手順をやるなど、非常にパーム筋を要する流石の構成だが、なににも増してディスプレイがキモい。
手遊びのカエルみたいな形状で、むにゅむにゅと指の間からコインが出てくるのだけれど、こんなの他に誰が考えつくかと。
というわけで、以降の巻にあるようなテーマ統一は無いが、技法的にも現象的にも、そして独特の美意識においても実にMcClintockといった作品集。このまま演じるのは、どうしてもためらわれるけれども、練習はしておきます。
2013年7月18日木曜日
"Close-up Framework" Lawrence Frame
Close-up Framework (Lawrence Frame, 1986)
クライマックスに重点を置いた、イギリスのマジシャン、Lawrence Frameの小冊子。
この人については経歴も消息もよく分からない。8手順中、演出のみが1つ、Sadowitzの寄稿作品が1つ。
うん、まあSadowitz作品を探していて見付けた本だ。ただそれだけなら買わなかったろうが、惹句に興味をそそられた。
”例を一つあげよう。Spellbound Climaxでは、2ペンス硬貨が10ペンス硬貨に変化し、また戻りを繰り返した後、いつのまにかコインがボタンになっている!.見下ろすと、ジャケットのボタンがあるべき場所に、コインがくっついている。”
これいいなあ、と思ったのだ。買って読んでみると、他のもなかなか好み。
”クライマックス”と言うと、どうにも手順が終わった後にもうひと山を加える(ツイスト)ものが多いけれども、これは手順の最終段をより派手に、あるいは豪華にしたといった所か。
クライマックスを付けるために無理をしたり、あまりそぐわないクライマックスだったり、ということは多いが、Frameのはあまり大変な仕込みも無く、現象としても違和感なく繋がっていて好きだ。
スペルバウンド、Twisting the Aces、Coin Cut、Card Acrossといったクラシックが、ちょっと予定調和的だったり、ラストがはっきりしないなあと思う人なんかにはおすすめ。ただしクライマックス部分のみの解説で、手順が載っていない物もあるので、ある程度知識は必要。またCoin ThroughTableは演出のみで、おまけにアイルランド人がうんぬんという話で正直これは流し読み。
全体として、特殊な技法をつかうわけでもないし、素材というか現象のつなぎが上手い感じで、もう少し別の作品も見てみたいのだが、他には露出がなさそうで残念である。
なおSadowitzの手順は、4つに分けたパケットに、1枚ずつAを配ってから重ねるが、Aは4枚とも一番上に上がってくる。それを相手にもやってもらうが、おなじように上がってくる。というもの。
うむ、これもなかなか。
2013年7月10日水曜日
"Penumbra issue 9" 編・Bill Goodwin & Gordon Bean
Penumbra issue 9 (編・Bill Goodwin & Gordon Bean)
Bill goodwin編集のマニアック・マガジン第9号。
技法多めのためか、作品点数はいつもより一個多いです。
Muy Bueno Shuffle:BJ Bueno
最近流行りの某フォールス・シャッフルをテーブル上で行う。非常によいと思いますので、あえてあまり踏み込まない。内緒です。上手く行うのは難しいですが練習。
Simulated Slip Cut:Allan Ackerman
スリップカットって正直あからさますぎるよね、って事で、ランニングカットに紛れ込ませた物。確固たる技法というよりも、Ackerman流のハンドリングといった程度の印象。上のMuy Bueno Shuffleとも相性がよいです。
Covered, Up!:J.K. Hartman
これはトリックですが、ほとんど単一技法に依っているので技法扱いでもいいくらい。コントロールなどの説明は大幅に省かれているからなおさら。
ハンカチでデックをくるみ、もう一度開けると、相手のカードかトップに表向きで現れている。
見覚え有るなあと思ったらCard Dupery にも収録されてました p.144。
Bertram, Braue and Ben:David Ben
我が身の浅学、技量のつたなさ、計算力のなさに打ちのめされるギャンブル・デモ。スタッドポーカー(4ハンド)、スタッドポーカー(6ハンド)、テキサス・ホールデムの3段からなる。Second Deal、Table Hop、Table Faroを駆使した4 of a Kind コントロール。構造はシンプルで無駄が無く、まさに”見えない超絶技術”のデモといった感じ。
特にBertramによるマルチプル・シフトから始まる最初のスタッキングは、相当にディセプティブ。
ただ少々問題があり「私はBertramの未発表のFaroを使っている(解説無し)」とか、「ここではFinlayのTable Shiftを使う。C.ジョーダンの本の5頁に解説がある」など、使用技法が解説されない事が多い。「良い技法だよ!」とだけ言われて歯がみすることしきり。あんまり古典もってない私の勉強不足が露呈する。
技術的にかなり難しいし、覚えなくてはならない事もちょっと有る、そのうえで現象と呼べるような物は特にない純たるギャンブル・デモなので、ある種のつまらなさはあるかもしれない。
でもこれ、一段目だけでも出来たらかっこいいなあ。
The Maddox Stack:Michael Maddox
David Benのとは対照的に、全く技法の要らないAny Hand Called for。
相手が役を選んだあと、一切のハンドリングが必要ない。それを達成するためのちょっとした工夫は、ささやかな発想の転換が良くできたミステリのようで非常に面白かった。ショーアップ次第でシグネチャー・ピースになりうる手順と思う。
技法多めだった第9号。Bueno ShuffleもBertramのShiftも、さすがはPenumbraといったクオリティ。いやでも個人的にPenumbraに求めているのは、洗練された”手順”なのですよ。そういう意味ではちょっと物足りなくもあった。
2013年7月8日月曜日
"奇術探究 創刊号" 編・ゆうきとも
奇術探究 創刊号(編・ゆうきとも、2008)
現代的で刺激的な表題作とあと何か。
福田庸太による変わり種のO&W「水漏れと油漏れ」にフューチャーしたノート。
このプロットがとても面白い。
赤4、黒4で水と油を始め、徐々に枚数を減らして3・3、2・2としていく。
ところが最後になって、赤黒赤黒とかみ合わせたはずのカードが4枚とも黒になり、捨てたカードが赤4になっているというオチ。意外ではあるが合理的というか、うまく意識からハズされている感じがたまらなく素敵だ。
というわけでこれは凄く良いのですがその後がちょっとついて行けない。
殆どずっと、ゆうきとものゆうきともによる(ゆうきとものための?)バリエーション。
原案がカウントを排することで”ごまかし”の気配を消し、ラストを引き立てていたのに対し、ゆうきとも案は基本的にクラシックな技法の組み合わせで、プロブレムの解としては成立していますが、どうなんだろうねえ。特に遺漏での「各段階の説得力はやや弱くなったけれど、手順の目的は最後のオチなので、これくらいのほうがバランス良いのでは」という点については、個人的には全く逆の理解。
まあ他のO&Wと組み合わせたいという人も居るでしょうし、そのためにハンドリングの毛色が違うのも1手順くらいは有ってもいいとは思う、と擁護できなくはないか。けれどもね、漏水は記憶を頼りに3時間で再構成した手順と言うし、このノートの原稿自体、原案を見てから2週間しか経っていないそうな。
それは作品では無くただの習作ではないですか?
いやしかし、水漏れと油漏れはすごく面白いです。これのためだけに買っても損はない。
ただ、今やトリックサウルス(未見だけど)出てしまったし、あれ安いしなあ。「水漏れと油漏れ」に対してどう試行錯誤するかを愉しみたいという奇特な人にも、いろんな寄稿者を迎えた奇術探究5号が出ているようだし。とりあえず奇術探究 そろえたいって人か、あくまで文章で水漏れ油漏れ読みたいという人以外には、あまりメリットのない冊子になってしまった。
とはいえ文章で情報をストックできるのは個人的に非常にありがたく、映像よりも見直しが楽ですし、実際、表題作はよく読み直している。レイアウトもとてもよく、読みやすいです。
追記・スイッチ無しで変則オチのO&Wというと、同書では名前上がってなかったけど、SkinnerのOil and Water Rides Againとかも良いですね。
2013年6月25日火曜日
"Penumbra issue 8" 編・Bill Goodwin & Gordon Bean

Penumbra issue 8 (編・Bill Goodwin, Gordon Bean, 2004)
碩学Bill Goodwinの発行するマニアック・マガジン Penumbra。その第8号。
と言うことで、引き続きPenumbraのレビュー。
今回も18頁で4作品を収録。
Constellation Prize:Justin Hanes
相手に夜空の星座をなぞってもらい、行き着いた星を予言している。
非常に古典的な原理を、怖ろしくロマンチックで壮大な現象に仕立てている。条件はそれなりに多いが(北半球、晴れ、光害小、相手方に視力とある程度の星座の知識などなど)、この発想はとても面白いですね。壮大と言えばGarden of the Strange という気宇壮大な本もあったが、あれよりも品があり、まだアマチュアでも出来る感じ。ただ最大の必要条件として、心・技・体の少なくとも一つが並はずれて男前じゃないと無理と思うので僕はちょっと出来ません。
予言マジックの筈がギップル召喚になりかねない。
相手に夜空の星座をなぞってもらい、行き着いた星を予言している。
非常に古典的な原理を、怖ろしくロマンチックで壮大な現象に仕立てている。条件はそれなりに多いが(北半球、晴れ、光害小、相手方に視力とある程度の星座の知識などなど)、この発想はとても面白いですね。壮大と言えばGarden of the Strange という気宇壮大な本もあったが、あれよりも品があり、まだアマチュアでも出来る感じ。ただ最大の必要条件として、心・技・体の少なくとも一つが並はずれて男前じゃないと無理と思うので僕はちょっと出来ません。
予言マジックの筈がギップル召喚になりかねない。
A.M.:Norman Gilbreath
前号の Harrison KaplanによるMirrorskillのヴァリエーション。構成、現象はほとんど同じだが、第二段での補正手法が異なる。One Way Deck使用。個人的には前号ので十分。
なおMirror Skillでのペア生成原理、およびNG状態の発生条件と処理方法を解説しているのだがこれは読み飛ばしてしまいました。しかしGilbrethって存命だったのですね。氏の名を冠した原理が有名すぎて、なんだか100年くらいは昔の人だと思ってた。
なおMirror Skillでのペア生成原理、およびNG状態の発生条件と処理方法を解説しているのだがこれは読み飛ばしてしまいました。しかしGilbrethって存命だったのですね。氏の名を冠した原理が有名すぎて、なんだか100年くらいは昔の人だと思ってた。
The Card of Fortune:Andrew Galloway
相手にカードを混ぜてもらった後、1枚のカードを抜き出し、後ろ手にそれを差し込む。差し込んだところから、相手のクリスチャンネームを綴り、そこのカードを裏向きのまま出す。もう一度繰り返した後、今度は相手にも同じような事をやってもらい、最終的に出てきた4枚のカードが、同一値になっている。
序盤の原理と、ちょっとしたサトルティは面白いが、「同じ事」ではなく「同じような事」なのがネックで、これはちょっと美しくない。
相手にカードを混ぜてもらった後、1枚のカードを抜き出し、後ろ手にそれを差し込む。差し込んだところから、相手のクリスチャンネームを綴り、そこのカードを裏向きのまま出す。もう一度繰り返した後、今度は相手にも同じような事をやってもらい、最終的に出てきた4枚のカードが、同一値になっている。
序盤の原理と、ちょっとしたサトルティは面白いが、「同じ事」ではなく「同じような事」なのがネックで、これはちょっと美しくない。
The Queens:Bill Goodwin
4枚のQが1枚ずつ消え、また1枚ずつ現れる。
Goodwinのペット・トリックなのだろう。全18頁のPenumbra、実にその半分を使ってみっちりと解説されている。技法の度に詳細なクレジットが挿入されるのが、さすが学究派といった所か。難しいが、実に美しい手順。Buckの双子が改案を出していますが、よりゆっくりと行われるGoodwinの方が好みです。ただ出現に関しては、ペースアップして一気に出した方がテンポ良いかもですね。
Penumbraは個人発行の雑誌にしては珍しく、筆者自身はほとんど作品を発表していません。いま手元にある4冊の中で、Goodwinの手順はこのThe Queensのみ(Gordon Beanに至ってはゼロ)。そういう所からも、本手順に込められたGoodwinの自信がうかがわれます。
4作中、2作はちょっと今ひとつでしたが、それら補ってなお、Constellation PrizeとThe Queensは凄い手順でした。
4枚のQが1枚ずつ消え、また1枚ずつ現れる。
Goodwinのペット・トリックなのだろう。全18頁のPenumbra、実にその半分を使ってみっちりと解説されている。技法の度に詳細なクレジットが挿入されるのが、さすが学究派といった所か。難しいが、実に美しい手順。Buckの双子が改案を出していますが、よりゆっくりと行われるGoodwinの方が好みです。ただ出現に関しては、ペースアップして一気に出した方がテンポ良いかもですね。
Penumbraは個人発行の雑誌にしては珍しく、筆者自身はほとんど作品を発表していません。いま手元にある4冊の中で、Goodwinの手順はこのThe Queensのみ(Gordon Beanに至ってはゼロ)。そういう所からも、本手順に込められたGoodwinの自信がうかがわれます。
4作中、2作はちょっと今ひとつでしたが、それら補ってなお、Constellation PrizeとThe Queensは凄い手順でした。
2013年6月21日金曜日
"Penumbra issue 7" 編・Bill Goodwin & Gordon Bean
Penumbra issue 7 (編・Bill Goodwin, Gordon Bean, 2004)
Magic Castleの司書を務める碩学Bill Goodwinが編集するマニアック・マガジン、Penumbra。
Goodwinについては、少し前にReflectionというDVDを見て以来、ちょっと興味があった。加えて先頃、Penumbra の9号に掲載されたというMuy Bueno Shuffleの動画を見る機会があって、それがまあ考えなくは無かったけど実行できるとは思ってなかった技法で、うわスゴイやと。こういうのが他にも載ってるなら、読んでみたいなあ。
そんなわけで、いまからでは揃わないだろうが買ってみた。
まあマニアックでしたよ。
Acorn's Progress:Roy Walton
Walton先生の小品。技法の用途と効率は素晴らしいのだが、現象にはさっぱり魅力を感じない。
手の中でカードを広げ、1枚表にする(スペードの10)。カードを閉じ、再び広げるとスペードのロイヤル・ストレート・フラッシュが表向きになっている。それらをテーブル上に出すが、よく見ると4枚しかない。デックを弾いて再び広げると、最後のスペードのAが表向きで出てくる。
Mirrorskill:Harrison Kaplan
通常のミラスキル(枚数の差を予言)→アキュレイト・ミラスキル(それぞれの枚数を予言)→さらに半分のカードだけで繰り返すが……
フルデック配らせるトリックを3回連続でやります。
ただし現象は面白いので、これが許される雰囲気でさえ有れば使えそう。それにペアで全部配り通して、色を判別するだけなので、そこまで負担でもないかな。セットもほとんど要らず、そういう意味では以外と手軽。Stewart Jamesの未解決プロブレムに対する解だそうです。
The Gypsy Foretells Further Than Father:Cushing Strout
Lie Detectorから、プロダクションへ続く長手順。
タロット的な占いが一緒に書かれたカードを使い、相手にカードを1枚選んでもらう。演者には見えないが、幸運の星が書かれたスペードの2。これを戻して混ぜる。相手の返答に合わせて、色、マーク、絵札か数か、の3つの山を作る。相手は嘘を言っても良いが、それぞれ選ばれたカードと同じパラメータのカードが現れる。
さらにTwo、Spade、と配ると、それぞれ3枚の2、5枚のスペードである。
ところで星に先端は幾つあった?と聞き、その数に合わせて配ると、そこからスペードの2が出てくる。 これは最高に運が良いぜ、こういうときはポーカーをやんな、と言ってpokerと配ると、その5枚がロイヤルストレートフラッシュ。
長いぜ。しかしよく考えましたねこんなの。これもベースはStewart Jamesとか。
Ear Candy:Nathan Kranzo
口にグミを含み、耳から指を突っ込んで取り出す。
指が口を内側からまさぐっている感じを再現しており、ハマると相当気持ち悪そうです。
Déjà Vu Cut:Chris Randall
三角を2つ作るフラリッシュ・カット。実はフォールス。
文章+写真の解説ですが、十分わかりやすいです。
Slap!:Shahin Zarkesh, Bill Goodwin
Aの間に挟んだ相手のカードが消え、ポケットから出てくる――、と思いきや。
正式名称をよく知らないですが、Off Balance Transpoとか、Imbalance Transpoとか言うのでしょうか。Bebelがよくやっている、4枚と1枚のトランスポジション。
トランスポが派手なのでそこに観客も読者も創作者も目が行きがちですが、この作品はその前の段階がとても丁寧に作られています。最初のディスプレイだけ、やや弱いと思うのですが、そこさえ上手くこなせたら、相手の手の中で選ばれたカードが消える箇所はとても効果的。
私などだったらElmsleyを使うような所で、ことごとく違うカウントを持ってくるあたり、マニアだなあと。こういうのをさらっとやられると、追えなさそうです。最後のトランスポジションも何通りか解説されていて面白い。
うむ、文句なくマニアック。ページ数はたった18頁ですが重い内容です。特にセルフワーク系のは、マジシャンでも追えない感じで、たいそう嫌らしい。とっておきのFoolerを探している方とか、こっそり手に取ってみてはいかがでしょうか。あと何冊か買いましたので、またおいおい紹介していきたいと思います。
2013年6月20日木曜日
Six. Impossible. Things.のおまけ
よくトップから2枚目とかにリバースカードがあって、それをデックの真ん中から出現させたいシチュエーションがありますが、そこでCharlier Cutするの嫌なんですね。S.I.T.だとCounterpunchの状況がまさにそれ。
特にHead Over Heelsとか、かなり効率的な技法なので、ここから余分な動作をしたくないなと。で、ここは以下のように変えています。
技法としては基本的な物で、この用法もどこで読んだか思い出せないです。
2013年6月18日火曜日
"Six. Impossible. Things." John Bannon
Six. Impossible. Things. (John Bannon, 2009)
John Bannonによる、極めて良く出来たカードマジック・レクチャーノート。
はい、すっかり啓蒙されたので買いました読みました素晴らしかった。いくつか既読のがあり、個人的にややインパクトが薄れてしまいましたが、それでもコスパ含めて過去読んだBannon本で最高の一冊。
『数個のカードマジックからなるルーティン』『セルフワーク作品集』『おまけ』と大まかに3部構成になっている。とすれば同じBannonのDear Mr. Fantasyに似ているが、DMFでは主にクラシック・トリックをつないだルーティンだったのに対し、こちらはフルBannonというのが大きな違い。
Counterpunch-Four Faces North
Watching the Detectives-New Jax-Full Circle
前半は既読でした。思い出せないけど昔とってたMAGIC誌かと。
サカートリック風味に観客の予想を裏切る手順から始まり、そこで残ったダーティな部分を解消するトリックへと続く。
後半はサンドイッチ・カードがテーマ。こちらも予想を裏切るスタート。2枚のJ、及び4枚のAから選ばれた1枚をばらばらにデックに差し込み、今からJがAを捕まえるぜ、と言うのだが、関係ない残りのAと思っていた3枚が、いつのまにかJ A Jになっている。
Wesley Jamesの原案は知らないのですが、最近Tom StoneのVortexで改案を読んでおり対比としても面白かった。Stoneが相手の見ているかもしれない状況で大胆すぎる事をして、大幅なスリムアップを図ったのに対し、Bannonは同じ”相手の見ている前で堂々と”ではあるものの、決して大胆ではなく、じっと見られていても大丈夫。
いや大胆ではある。ですが、まず気付かれない。どうやったらこんな事を思いつき、実行してしまえるのか。いやはや凄い。
この、相手の目の前でぬけぬけと、明らかにおかしい事をしかし露見せずやってしまう、というのはBannonの特色であり、また演じる者にとっては非常な快感でしょう。
なんかBannonの玄人受けの一因を再確認したように思います。
っていうか、こういうちょっと奇矯なプロットって、作例の絶対数が少なくて叩き台が無いためでしょうけど、どうにもぎこちない、不自然な構成になりがちなところ、まあBannon先生のうまいことうまいこと。
全体を通すと、4枚のAから始まり、4枚のAで終わる、美しい構成。
この一連の流れは、少しマジック囓ってるぜって人とかを相手に見せたい。
ただプレゼンはあまり解説していないので、ちょっと考えないといけません。ヘンな現象ばかりなのでけっこう大変かもしれない。
Four-Fold Foresight
Origami Poker Revisited
Bannonのお気に入り、Origami Foldの原理を使った2手順。この前者がとても良かった。観客が表裏ぐちゃぐちゃに混ぜたパケットの状態が予言してあるというもの。
原理がOrigami Fold、現象がShuffleBored。どちらも好きな手順では無かったのですが、この組み合わせがそれぞれの(個人的に感じていた)欠点を補い合っている感じで、これは凄くよいです。
Riverboat Poker
ポーカーデモンストレーション。やりやすいし、見やすい、良い手品です。格式張らない自然さで、あくまで「話の種に」という感じがとても受け入れやすい。ロイヤル・フラッシュのオチまで付いている癖にセットアップが殆どいらないという親切設計。
ここだけ、解説が小説風です。
Play It Straight (The Bannon Triumph)
あえて説明も要らないだろう傑作。これを駄作とみる向きもおられますし、前は僕もそっち寄りでしたがやはり凄い手順です。ただ解説は簡潔で、Impossibiliaで感心した細かいタッチが抜けてしまっておりちょっと残念。
Einstein Overkill
Trick That fooled Einsteinの改案。そもそも原案があまり好きでは無いのですが、このアイディアはすごく面白い。Bannonは4 of a Kindの出現に仕上げていますが、純粋な形態であればメンタル度が格段に上がって、好みかも。
というわけで長々と書きました。本当はもっと簡潔に書ければ良かったのですけれどもまあとにかく面白かったよーと。これが15ドルやもんね、すごいね。
個々の収録作品も良いのですが、それ以上に『オフビートなトリック』『ルーティンとしての構成』『セルフワーク』『小説風の解説』『Play It Straight』と、Bannonのエッセンスを抜き出して煮詰めたような、小ボリュームながら極めて充実した内容が素晴らしかったです。
サイトではLecture noteと書かれており、いやなんかそれだと適当なトリックを適当な体裁の紙束に適当にぶちこんだみたく聞こえてしまいますけど、実際には造本も内容も構成も、とてつもなくもハイレベルなカードマジック教本でございました。
余談ですが、↓にShuffle Boredの嫌いな点の話をちょこっと。
2013年5月24日金曜日
"MEGA 'WAVE 日本語版" John Bannon 訳・富山達也

MEGA 'WAVE 日本語版(John Bannon、訳・富山達也、2011)
John Bannonによるエンドクリーンな7つの改案集。
唐突にBannonが(手頃な値段で)読みたい、精緻なカードトリックがいじりたい、ともかくカウントしたいという欲望がこみ上げたので、今更ながら購入。テクニカラー・パケットとか作るの面倒ですが、訳者様ご本人から購入すれば無料で付いて来るというお話だったので、おそるおそる連絡してみました。
パケットは直接購入の特典、との事だったのでつまり直接手渡しオンリーかと思っていたのですが、伺ったところ、いや普通にメール便で送りますし今までも通販が主でしたよとの事。
そうなのか。きょうじゅさんがブックレットをファンにしてかざしたらば、都下県下のバノンに飢えたマニアどもが亡者がごとくにむらがって、瞬く間に跡形もなくなるかと思っていた。なんとなく。
さておき内容。エンドクリーンと書いたが、正確には少し異なったコンセプト。パケット化が可能で、全てのカードが能動的に現象に寄与し、何かを足したり除いたりせず、最後に改めも可能というこの構成を、Bannon自身はフラクタルと名付けている。
作品数は7と少なめで、また現象に偏りはあるものの、内容としては非常に充実していた。
せっかくなので全作品に言及してみるが、あまり中身無いので飛ばしても良いです。
ここから↓
MEGA 'WAVE:
BannonというとTwisted Sistersが有名だが、あれに類縁の2組での4 Card Brainwave。Twisted Sistersに引けを取らない現象でありつつ、検め可能。個人的には、このプロット自体にちょっと煮え切らない物を感じるのだが、Bannonのは狙いが定まっており、実用してみたくなります。
Fractal Re-Call:
自身のCall of the Wildの改案。Wildとはいうが、持ってるハンドが全て変化するというギャンブル系の現象。原案と遜色ないながらギミックが排されており、凄いです。変化現象にAsher Action Reverseを使う箇所の考察が、個人的にはとても面白かったです。
Short Attention Scam:
これも御自身の単品作品Royal Scamの改案で、序盤のTwist現象を省いた物。これは原案も含め、あまり現象に起伏が感じられず、どうにもピンときませんでした。しかしRoyal Scamはお客さんが(反応含めて)可愛いくていいですね。
Mag-7:
これまた過去作Return of the Magnificent Sevenの改案。鮮やかでスピーディな、ギミック無しのワイルドカード。個人的なベストWildは、まあお察しの通りWonder演ずるTamed Cardなのですが、このMag-7くらい軽やかに畳みかけるのも良いなと。
Poker Paradox:
いわゆるRoyal Marriages系作品。つい先頃まで退屈なプロットという認識でいたのですが、Juan Manuel Marcosがある特別なタッチを加え、非常に鮮やかな現象に変貌させており、気に入って演じておりました。ただ唯一、観客が参与しない点だけ気になっていました。
一方こちらのPoker Paradoxは、手法はオーソドックスなものの、非常に狡猾な組み合わせによって実に不思議に仕上がっている。正直、自分でもやってて不思議。
なによりお客さんが関与するのがよいですね。MarcosのLa Claridadと、どちらを取るか非常に悩ましいです。
Fractal Jacks:
デックの一番上にJackが4枚置かれた後、交互に手を配ったはずなのに、なぜか何度やっても手元にJackが集まっている。という妙な不条理感のある現象が元。これを8枚のパケットでやってしまう。
あえてクライマックスを殺す構成になっており、SolomonやAronsonからは賛同を得られなかったらしいですが、僕はこちらの方が好きです。ただし、借りたデックや自分のデックでも出来ますが、パケット化しないと効果を十全に発揮できない気がします。
Wicked:
Jack ParkerによるI know Kung Fuの、見る影も無いほどスマートな改案。原案の無茶な感じはけっこう好きでしたが、Bannonが触るとこういうふうになるのですね。
2段からなる、シンプルなサンドイッチ。
↑ ここまで
またコンセプトとして、フラクタルの他にスラッグというものを要所要所で使用。
これはセットしたカードを導入するやり方についてのアイディアで、Play It Straightの作者ならではというか、既存のやりかたからあえて後退することによって見えてくる有用性という所でしょうか。賛否両論ありそう。
さて作品そのものもよかったけれど、Bannonの解説がなにより素晴らしかった。改案の動機から現象のたくらみまで、細やかに解説しており、それが一番面白く、また実演してみたいという動機にも繋がりました。
特にStephen Tuckerに対する駄目出しは、始めこそ柔らかく切り出したものの、徐々に舌鋒が鋭さを増していくあたりが大層面白い。と同時に、非常に的を得た論評であり、世にはびこるマジック・クリエーターのなかにおいて、Bannon作品の極めて高い練度がどこから来るのかを垣間見るようでもありました。
一方で、現象の偏りというか、フレーバーとしてポーカーを好む点だけはちょっと苦手です。ただこれは適当なテーマに置換してしまえばよいのでしょう。特に本書の手順は全てフラクタル、独立した構造になってます。スラッグ・コンセプト含めて、このフラクタルというやつ、特殊柄のパケットトリックとも相性が良いと思います。もっといえば、いわゆる痛手品とかバカ手品とかの改案作り放題な気がしなくも無いので誰か作って下さい頭悪い手品。
ともかく、とても満足しました。Bannonやっぱり面白いぜ。
直ぐに読み返せるのも想像以上にありがたく、日本語訳の、それもこなれた文章であることの利点でありましょう。ときおり中の人が漏れ出てましたが、とても読みやすく面白かったです。
Dear Mr.Fantasyも翻訳中とのことですが、いや適任と思いますきょうじゅさま。あの小説っぽいところとか。
唯一、値段が高くなってしまうのがちょっと残念というか、おまけパケット無かったら本家で買ってしまうよなあと。発行部数とか考えると仕方ないのでしょうし、本家が安すぎるだけという話もありますが。
初期目的の一つであったカウントはあまり無く、残念でしたが、これはどうも過去のフラクタルシリーズ、およびLiam Montierとの共著Triabolical と混同していたようでした。
ともあれすっかり啓蒙されました。他の著作も早急に集める所存です。
登録:
投稿 (Atom)