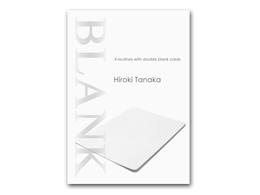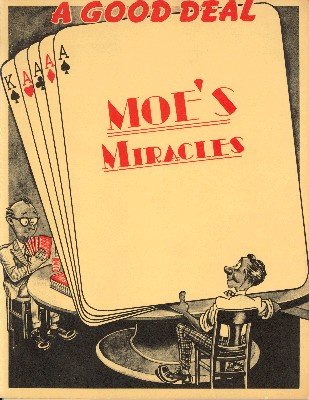Dear Mr Fantasy(John Bannon, 2004)
John Bannonのカードマジックオンリーの作品集。
実は日本某所で邦訳が進んでいると聞いてはいて、そちらを待機するつもりだったのだが、安かったのでついつい買ってしまった。
さて本書、一部では評判が極めてよく一部では評判が芳しくない。
まあなんにしたって賛否両論はあるだろうが、ベスト本の一つに上げる人がいる一方で、後者では読んだ後つまらないので捨てた(後に買い直した)などと自慢話のように書いておられる方もいるくらいには振れ幅がある。
内容は例によってオフビート、サトルティに重きを置いた整った構成の作品が多いが、今回は貴基本的にクラシカル。和訳される事もあり、せっかくだから各章解説してみよう。
・Bullet Train
タイミングをずらした4Aアセンブリ×3。
レイアウトが終わった瞬間に手札を返すと集まっている。
Greenの4Aプロダクションを模倣したとのことだが、その点ではあまり成功しているようには思わない。
どちらかというと、アンビシャスカードからマジカルジェスチャーを抜いただけという印象。
まあレイアウトした時点でアセンブリが終了している、というマジシャン側の思い込みに起因しているのかも知れないが、今ひとつ気に入らなかった。
手順構成自体はさすがにうまい。
・The Secret and Mysteries of the Four Aces
シャッフルされた状態から始められる一連の手順。
カード当て、観客がカットする4A、Twisting AcesとLast Trick(Tipsのみ、解説は無し)、Crist Acesにロイヤルストレートフラッシュが出てくるエンディング。
クラシカルなトリックを淀みなくつなげた、カード屋のお手本のようなルーティン。実際の運用ってあまり書かれないのでこれは良い資料と思う。
・Dead Reckoning
巧妙に構成されたトリック3つ。
特に1つめのDead Reckoningは、これは当たるわけがないだろうって状況でのカード当て。スペリングでさえ無ければ……。だが構成を知るだけでも十二分に価値のある傑作。
またDawn Patrolは
Bullet After Dark DVDのデモで見られるが、何となくの構成は判っても詰め切れなかった作品。この2作で使われているコントロールは実に巧妙で、かつ外見上の不自然も殆ど無く優秀。
解説が小説っぽいのもこの章の特徴。全編このスタイルだとさすがにうんざりだろうが、1章分としてはよいアクセントであり、現象だけを記述するとつまらなく見えるメンタル寄り手順の解説スタイルとして、面白いアプローチ。
・Degrees of Freedom
ある原理に基づいたセルフワークトリックの章。複数解説されているが大同小異。
表裏ぐちゃぐちゃに混ぜたカードを並べ、それを観客の支持に従って畳んでいく。広げるとロイヤルストレートフラッシュだけが表向きになっている。
要するにはHammerのCATTOの最後を行列に展開するって事なのだけれど、これに関する評価いかんで、本書の価値が決まるのではないかな。これが初見であったり、この類の手順が演じられる人であれば、確かにこの本は傑作と思う。
が、
Card Magic Libraryで既読だった事に加え、個人的にはこれ、あまり好きではないのだよな。線形代数とか行列式とかを思い出させるのは別としても、煩雑さと効果でいうと、Foldingプロセスってどうなのかなぁ。
いつか見た、観客と縁者がそれぞれのパケットを混ぜた上で4Aが出てくるバージョンぐらいが一番バランスが良いと思う。あくまで個人的にだが。
解説はしっかりしており、事前セットアップをなくす方法や、原理自体の解説なども行き届いて勉強にはなる。
・Impossibilia Bag
その他のカードマジック。古典トリックに対して、すっきりとしたハンドリングや、角の立たないプレゼンテーション、無理のない現象の拡張などを図る。
Goodwin/Jennings Displayを使ったトライアンフ Last man Standingや、Gemini Twinsのラストに4Aが出てくるTrait Secretsが良かった。
・Lagniappe
おまけ。David Solomonの10カード ポーカー。タイトルの「Power of Poker」から、てっきりElmsleyのPower Pokerが下敷きかと思っていたが、難しい技法は排されており、Equivoqueなどもなく、なるほどなあと感心。
ただいつぞや松田道弘が書いていた「繰り返せる事が10 カードポーカーの肝」という観点からすると……。どうだろう繰り返せるだろうかこれは。
さて個人的には、あまり、面白くはなかったかな、という感じ。悪い本という意味ではないのだが、好みに合わなかった。
Impossibiliaでの、サトルティとオフビートな手法の限界を探るかのようなトリックを期待していたのだが、今作ではどちらかというと、既存手順をいかに簡易化・見た目に単純化できるかという方向性だったように思う。
また、自費出版だからか、レイアウト・フォントなど本の作りが今ひとつ垢抜けず、内容とは関係ないが、その点での心証マイナスが大きいのやも知れない。
というわけでマニアに対しては、自己責任で、といった本。
ただし初級から中級手前の人には強くおすすめできる。
現象は、4Aアセンブリやトライアンフ、ギャンブルデモと王道を揃え、それを実現する原理もテクニック、サトルティ、数理と広くカバーしている。しかもどれも使い方が嫌みなく上手い。創作として見ると、既存トリックの実際のつなげ方、手順の改良、現象の拡張とこれまた広い範囲をカバーする。
ともかく珍奇な技法が練習したい、というのっけからマニアな頭の人は別として、読んで損する本ではあるまいよ。