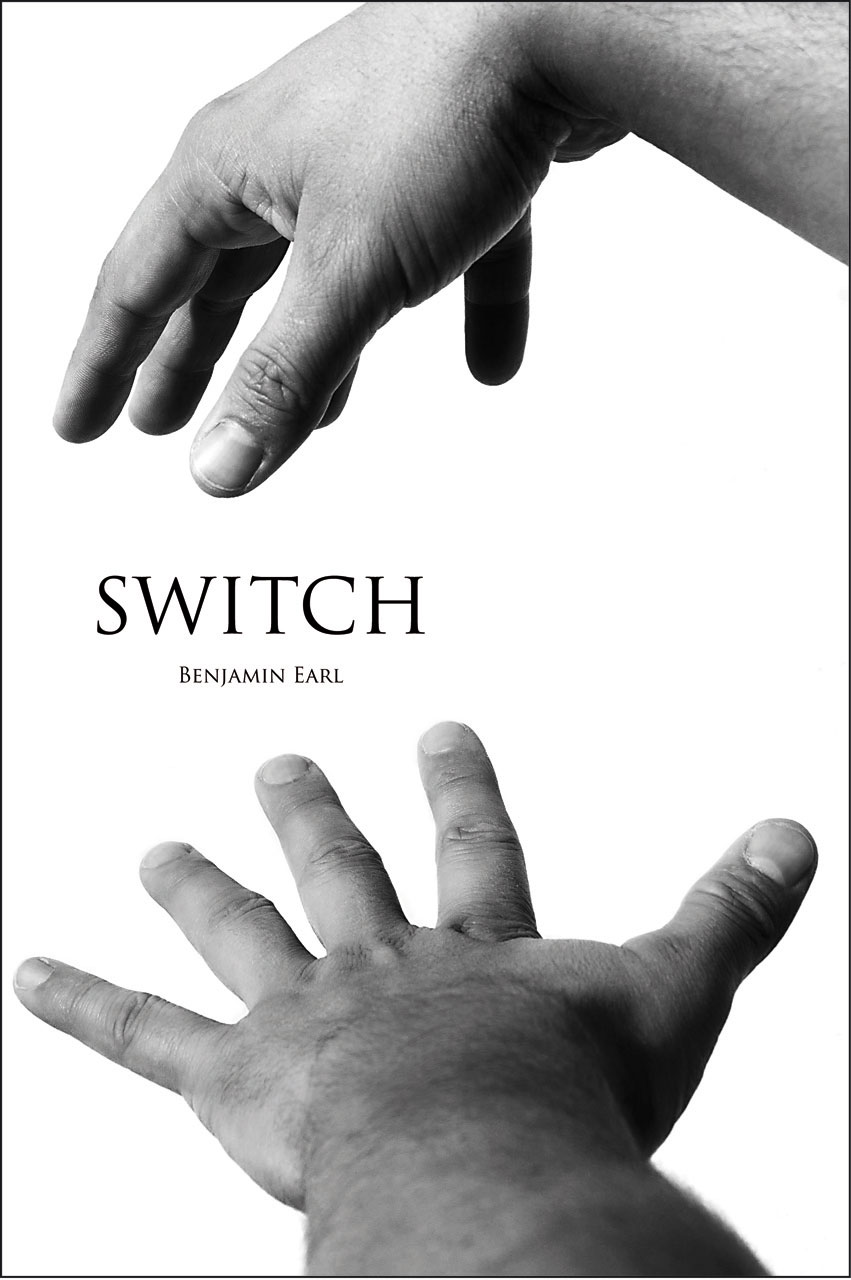Hector Chadwickが出版したパンフレット。
タイトルがめちゃくちゃ長いですがページ数は少ないです。意味は『マジックの世界でオリジナル作品を作ることに関して考える13のこと』という所でしょうか。内容はそのまんまで、オリジナルな作品を作るにはどうすればいいのか、13の基本的な考え方を紹介しています。
ところで創作論を語るなら、やはり実績あるクリエイターではなくては説得力がなあ……と思ってしまうのが人情です。でもHector Chadwickって何者なんだ。商品なんてひとつもヒットしないじゃないか(*)、という所なんですが、前書きを読みますと、『最近ではますます人前で演じる事は無くなってきたけれど、私は人生のそれなりに長い期間を、他のマジシャンの創作を助けることで生計を立ててきた』と。
この方、なにを隠そうDerren Brownのショーの共著者の一人なんですね。Brownのショーはローレンス・オリヴィエ賞(**)の受賞歴もあるすごいクオリティで、youtubeで公開されたりもしてるのでよければ見てください。ともかく業界トップクラスのクリエイターであることは間違いないでしょう。
(*Vanishing IncからEquivoqueのダウンロードがひとつ出ている)
(**イギリスにて、その年に上演された優れた演劇・オペラ等に与えられる賞。イギリスで最も権威があるらしい。すごい。Wikipediaより)
紹介されている創作の13箇条については、そこまで意外性のある話はありません。正道と言うのが良いでしょう。けれど非常に良く言語化されています。長く手品をやっていると、このあたりはなんとなく感覚的に分かってきますが、それを言葉にするのは意外に高いハードルです。また比較的早い段階でこういうのに出会うと、大いに助かると思います。
あと、本書はなぜか手書きです。カラーのサイン・ペンかなにかを模しており、インクを散らしたりなんかして非常にカラフルで目に痛いです。ただ字は綺麗+ブロック体なので意外と読みやすい。
なお再販予定はなし。というのも本書の内容については、いま書いている新しい本で詳述するからとのことです。だから無理して買う必要はないわけですが、非常に美しいパンフレットですし、新刊もいつに(そして幾らに)なるか分からないですし、けっこうお奨めです。